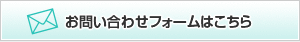#191 小澤征爾と西洋音楽
2024-02-24
指揮者の小澤征爾さんが今月初旬に亡くなりました。88才でした。
昨年9月の「松本音楽フェスティバル」にジョン・ウィリアムスが客演した際、歓迎のために舞台に車椅子で登壇した映像が小澤さんを見た最後の姿となりました。
学生時代からよく新日フィルの演奏会で常任指揮者として忙しい中をぬって指揮するのを何回となく見たのが思い出されます。
小澤さんの指揮者としての生い立ちはその著書「ボクの音楽武者修行」(新潮文庫)に詳しい。この本は今でも若い人たちに読んでもらいたいもののひとつで、若者の特権のひとつである失敗を恐れぬ行動力や好奇心の強さがよく描かれていて好感が持てます。彼の音楽人生は斎藤秀雄氏が主宰する桐朋学園短大の指揮科に入校したことから始まります。当初はピアニストをめざしていましたがラグビーで指を痛めてピアノを断念したのがその理由だったというのはいかにも小澤さんらしいエピソードです。
昭和34年に単身スクーターを駆って渡仏。この時のスクーターも現在のSUBARU製のものを日の丸を掲げることを条件に借り受けたもので、しかもフランスへは貨物船に乗っての船旅で費用を抑えたものでした。当地で最初の奥さんになるピアニストの江戸京子さんらの助言で、急遽ブザンソンという田舎町で行われる指揮者コンクールに応募しますが、その時はすでに締め切り後。それでもあきらめずアメリカ大使館に駆け込んで直談判し1週間後に出場権を獲得するいきさつは大いに若者には参考になります。そしてそのコンクールでいきなり優勝を勝ち取り、世界の音楽シーンに登場していきます。その後カラヤンコンクールでも優勝し弟子入り。さらにボストン交響楽団のタングルウッド音楽祭でのコンクールでも優勝しシャルル・ミュンシュにも師事します。昭和36年にはバーンスタインによってニューヨークフィルの副指揮者に抜擢され師と共に日本に凱旋帰国を果たします。そしてその翌年にはNHK交響楽団の常任指揮者に就任しますが、ここでかの「N響事件」が起き、順風満帆に進んできた小澤さんにとって最初の蹉跌となったことは有名です。才能ある指揮者といっても当時若干27歳の若造の生意気な態度に旧態依然の楽団が反発して演奏会をボイコットしたのが真相といわれ、新聞紙面に一人指揮台に立つ小澤の写真が掲載され世間にも知られるところとなりました。事件後小澤を励まそうと三島由紀夫や井上靖が企画した「小澤征爾の音楽を聴く会」では文字通り汗と涙で顔をくしゃくしゃにしながら指揮し、それを見た三島が「そら、ごらん、小澤征爾も日本人だ」と朝日新聞に寄稿しています。これを境に日本に見切りをつけて渡米し、トロント響、サンフランシスコ響、そしてボストン響と長いキャリアを積んでいきます。そして29年間君臨したボストン響の音楽監督を退いて、2002年ウイーン国立歌劇場音楽総監督に就任します。まさに世界のクラシック音楽の頂点に上り詰めたのでした。
斎藤秀雄が作り上げた指揮メソッドは理にかなったもので、その薫陶を受けた指揮者としての小澤のバトンテクニックは当代随一と言われました。再現性の高いその指揮振りは並外れた記憶力による暗譜と共に小澤の真骨頂を示すものでした。そしてなによりその明るく人なつこく飾り気のない人柄が周囲の人に愛され、多くの仲間に恵まれた理由だったような気がします。そうでなかったらボストン交響楽団で29年にも渡る長い期間音楽監督を続けることなどできなかったろうと思います。

朝日デジタルより
しかし順風に見える指揮者・小澤征爾ですが、その内面では常に棘の刺さった葛藤がありました。「日本人に西洋音楽が分かるのか?」という命題です。ルター派の教会音楽だったバッハを東洋人が理解できるのか、神を信奉し神のために音楽を書いたブルックナーの音楽をキリスト教を理解しない日本人が演奏できるのか、という問いかけです。これらはクラシック音楽を聴く側の問題としても当てはまるものですが、あるインタビューで小澤さんが語っている文章があります。
「その問題については誤解がないように申し上げますけどね、建前としては“音楽に国境はない”と言っている。だけど真面目に訊かれたときは“音楽に国境はない”では済まないと思うんです。僕自身が“実験”なんですよ。それはウィーンに行くことでますますそうなってきました。嫌な顔をする人もいるけど、僕自身は自分が西洋音楽をどこまで理解できるか、表現できるかの実験だと思っています。僕はね、自分が西洋音楽についてまだまだ分かっていないことがたくさんあることをよく知っているつもりです。・・・いちばん難しいのは、あまり言いたくないけど、精神性ってやつでしょうね。それは実験の最後になります。ところが日本人の精神性というのは、日本人は忘れているかもしれないけど、相当深いものがあると思う。戦争が終わって復興して、お金が増えて外国のものが入ってきた。平気でこうやってネクタイを締めてるし、平気で西洋の生活をしていますね。ベッドに寝て、洋式便所に入って・・・。それで日本人の精神性がなくなってるんじゃないかとみんな思っている。でもそれは錯覚じゃないかな。そんなことでどうにかなるほど、日本人の精神性はヤワじゃないと思う。僕らみたいに苦労している人間は、そこのところはどこか摑まえているんです。・・・なにも西洋の真似なんかすることはない。西洋人になんかなれっこないんだから。」(遠藤浩一著:小澤征爾日本人と西洋音楽・PHP新書から)
小澤征爾は西洋文明に帰依し、日本人であることを捨てることによって今日の地位を獲得したのではない。むしろ常に自分が日本人であることを自覚し、西洋音楽との測り知れない距離に苦しみ続けてきた。そこに強みがある、と喝破しています。
長い伝統に培われてきた西洋音楽にあって、良くも悪くも伝統のない日本の一風雲児が、戦後間もない時代に駆け抜けたその軌跡と苦悩の中に、涙と共に教えられることが多いのです。 合掌