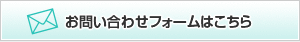#164 鷹山の地方自治
2020-11-20
その名を知ったのは30代初めの青年会議所時代に、当時の日本青年会議所会頭の京都会議での年頭所信でした。破産状態だった旧米沢藩を改革により蘇らせ、天明の大飢饉の折にも藩内からは一人の餓死者も出さなかったとされる名君がいて、後年アメリカの大統領に就任したJ.F.ケネディが記者から日本で最も尊敬する政治家は誰かと聞かれて、その人の名を挙げたと言われたのが「上杉鷹山(ようざん)」でした。
今は山形県に位置する米沢市はかつて会津とともに伊達氏によって治められていましたが、秀吉の奥州仕置によって蒲生氏郷に、そののち上杉氏にその所領が移り家老直江兼続が米沢に入ります。関ケ原後減封され120万石が一挙に30万石へ、さらには15万石へと減らされていきます。名家にありがちなかつての栄光を捨てられないジレンマに陥り、15万石になったにもかかわらず120万石体制の家臣団や慣習を引きずり藩財政は破綻し多くの借財だけが残る状態になっていました。嫡子が続かなかったため遠く日向高鍋藩から明和4年、第9代藩主として養子に入ったのが鷹山でした。
火中の栗を拾うという言い回しの通りの状況での家督相続は相当な覚悟と不屈の精神が要ったと推察されます。鷹山の改革を簡単に今風に言えば、緊縮財政と成長戦略、教育改革ということになるでしょうか。大倹約令を発布して自らの生活費も切り詰め食事内容から衣類、慣習儀礼なども細かく見直し奥女中もリストラしたとされます。殖産興業では農業土木の技術革新から墾田を進め多くの新田を開発し、稲作に不適な地には漆やコウゾの木を植えさせさらには養蚕の振興を図り絹織物の一大産地とすることを推し進めます。このほかにも鯉の養殖、紅花の栽培、最上川の舟運による交易などその振興策は枚挙にいとまがありません。教育においても世襲代官制度を改めて能力により人材を登用、それまでなかった藩校を創設して自らの師であった細井平洲を招聘し興譲館と命名します。授業料を取るどころか生徒一人一人に年1両の手当金を与え寄宿代も無料として将来の人材を育てたとされます。結果、鷹山が家督を継いだころにあった数百万両という借財は晩年隠居したころには返済し逆に5千両の蓄財を有するに至ったと言われます。当然改革には保守派の反発が付きもので、改革当初には七家騒動と呼ばれた家臣の反乱があったものの、人心の掌握と強い信念によりこれを失脚させています。
鷹山の社会改革には東洋的教えの一つと言われる「経世済民」思想があったと言われます。「経済」の原語と言われ、乱れた世を正し苦しむ民を救うという意味で経済と道徳を決して切り離さない点が美点とされます。富は常に徳の結果であり両者の関係は木と果実の関係と同じだと教えています。師である細井平洲の儒教思想によるものでしょうが、「大名とその家臣のために地域住民は存在していない。逆に地域住民のために大名とその家臣が存在している」というある種「主権在民思想」に近いものを、まだフランス革命も起こっていない時代に持ちえたというのは驚嘆に値します。人間愛に満ちた鷹山のヒューマニズムが地域におけるまちづくりにはなにが必要で、住み手は何をすべきかという点において真の地方自治のあり方を考える上でのヒントになるように思われます。
ケネディが鷹山のことを知ったのは内村鑑三が原文を英文で綴った「代表的日本人」という本からとされます。武士道を日本人の規範と説いた内村がその例として西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮上人と共に上杉鷹山を5人の代表的日本人として紹介したものです。そこには今は失われてしまったかもしれない「サムライ・スピリット」が生きる上での日本人精神のよすがとして記されています。多分に儒教的な気分の中で書かれてはいるものの自らクリスチャンでもあった内村がこれらこそ世界に通用する日本人の鑑と思っていたのでしょうし、ケネディもそれに共感したのだと思われます。
市の中心部のかつて平城だった米沢城址には上杉神社が建てられ、その唐門の手前に「為せば成る、為さねばならぬ何ごとも、為さぬは・・・」の遺訓と共に鷹山の立像が置かれています。また近くには米沢市上杉博物館があって上杉家の歴史と鷹山の改革の内容が寸劇映画も交えながらビジュアルに展示されており、なかでも春日山城由来の狩野永徳作の国宝「上杉本洛中洛外図屏風」が常設されているのが垂涎の展示品として出色です。
米沢藩は幕末会津藩と共に新政府軍に対峙、北越戦争にも巻き込まれながらもその後恭順に徹したため藩主茂憲は華族に列し伯爵を授けられ戦前まで続きます。大正期に焼失した後に建てられた上杉伯爵邸が今に保存され食事処として使われています。かつて東側からは栗子山を13号線で峠越えして行くしかなかった米沢ですが、現在は東北中央道の長い国境のトンネルを抜けると雪の心配もせずにあっという間に福島から入ることができるようになっています。大店舗法により多くの地方都市が大手資本の郊外店に席巻されて金太郎飴のように同じ景観を呈し特色のない街並みになってしまっていますが、この伯爵邸の周りには鷹山が奨励したウコギの垣根や池の錦鯉などが残され往時の面影を偲ばせてくれます。
今は山形県に位置する米沢市はかつて会津とともに伊達氏によって治められていましたが、秀吉の奥州仕置によって蒲生氏郷に、そののち上杉氏にその所領が移り家老直江兼続が米沢に入ります。関ケ原後減封され120万石が一挙に30万石へ、さらには15万石へと減らされていきます。名家にありがちなかつての栄光を捨てられないジレンマに陥り、15万石になったにもかかわらず120万石体制の家臣団や慣習を引きずり藩財政は破綻し多くの借財だけが残る状態になっていました。嫡子が続かなかったため遠く日向高鍋藩から明和4年、第9代藩主として養子に入ったのが鷹山でした。
火中の栗を拾うという言い回しの通りの状況での家督相続は相当な覚悟と不屈の精神が要ったと推察されます。鷹山の改革を簡単に今風に言えば、緊縮財政と成長戦略、教育改革ということになるでしょうか。大倹約令を発布して自らの生活費も切り詰め食事内容から衣類、慣習儀礼なども細かく見直し奥女中もリストラしたとされます。殖産興業では農業土木の技術革新から墾田を進め多くの新田を開発し、稲作に不適な地には漆やコウゾの木を植えさせさらには養蚕の振興を図り絹織物の一大産地とすることを推し進めます。このほかにも鯉の養殖、紅花の栽培、最上川の舟運による交易などその振興策は枚挙にいとまがありません。教育においても世襲代官制度を改めて能力により人材を登用、それまでなかった藩校を創設して自らの師であった細井平洲を招聘し興譲館と命名します。授業料を取るどころか生徒一人一人に年1両の手当金を与え寄宿代も無料として将来の人材を育てたとされます。結果、鷹山が家督を継いだころにあった数百万両という借財は晩年隠居したころには返済し逆に5千両の蓄財を有するに至ったと言われます。当然改革には保守派の反発が付きもので、改革当初には七家騒動と呼ばれた家臣の反乱があったものの、人心の掌握と強い信念によりこれを失脚させています。
鷹山の社会改革には東洋的教えの一つと言われる「経世済民」思想があったと言われます。「経済」の原語と言われ、乱れた世を正し苦しむ民を救うという意味で経済と道徳を決して切り離さない点が美点とされます。富は常に徳の結果であり両者の関係は木と果実の関係と同じだと教えています。師である細井平洲の儒教思想によるものでしょうが、「大名とその家臣のために地域住民は存在していない。逆に地域住民のために大名とその家臣が存在している」というある種「主権在民思想」に近いものを、まだフランス革命も起こっていない時代に持ちえたというのは驚嘆に値します。人間愛に満ちた鷹山のヒューマニズムが地域におけるまちづくりにはなにが必要で、住み手は何をすべきかという点において真の地方自治のあり方を考える上でのヒントになるように思われます。
ケネディが鷹山のことを知ったのは内村鑑三が原文を英文で綴った「代表的日本人」という本からとされます。武士道を日本人の規範と説いた内村がその例として西郷隆盛、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮上人と共に上杉鷹山を5人の代表的日本人として紹介したものです。そこには今は失われてしまったかもしれない「サムライ・スピリット」が生きる上での日本人精神のよすがとして記されています。多分に儒教的な気分の中で書かれてはいるものの自らクリスチャンでもあった内村がこれらこそ世界に通用する日本人の鑑と思っていたのでしょうし、ケネディもそれに共感したのだと思われます。
市の中心部のかつて平城だった米沢城址には上杉神社が建てられ、その唐門の手前に「為せば成る、為さねばならぬ何ごとも、為さぬは・・・」の遺訓と共に鷹山の立像が置かれています。また近くには米沢市上杉博物館があって上杉家の歴史と鷹山の改革の内容が寸劇映画も交えながらビジュアルに展示されており、なかでも春日山城由来の狩野永徳作の国宝「上杉本洛中洛外図屏風」が常設されているのが垂涎の展示品として出色です。
米沢藩は幕末会津藩と共に新政府軍に対峙、北越戦争にも巻き込まれながらもその後恭順に徹したため藩主茂憲は華族に列し伯爵を授けられ戦前まで続きます。大正期に焼失した後に建てられた上杉伯爵邸が今に保存され食事処として使われています。かつて東側からは栗子山を13号線で峠越えして行くしかなかった米沢ですが、現在は東北中央道の長い国境のトンネルを抜けると雪の心配もせずにあっという間に福島から入ることができるようになっています。大店舗法により多くの地方都市が大手資本の郊外店に席巻されて金太郎飴のように同じ景観を呈し特色のない街並みになってしまっていますが、この伯爵邸の周りには鷹山が奨励したウコギの垣根や池の錦鯉などが残され往時の面影を偲ばせてくれます。