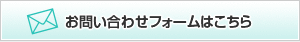#201 大和路の古寺あるき-2
2025-03-10
前回に続いて奈良・大和路の古寺歩きの続きを紹介させていただきます。
まず薬師寺です。なんといっても創建当時のままを残す東塔の解体修理が終わったのを見ることです。白鳳様式を伝える数少ない建物の一つであり卓抜な意匠を示す日本建築の至宝として最高の賛辞を捧げても、なお足りることをしらないと賞されているものです。大小の屋根が交互に出入りする裳階が付けられた特異な構造形式でその幻想的なさまから「凍れる音楽」と賞されていることは有名です。心柱の脚部の傷みが顕著であることから史上初の全面解体による保存修理が行われ12年ほどかけて2021年に終了したばかりです。法隆寺の五重塔と比べて、その技術水準が2~30年ほどの時間差に関わらず格段に進んでいることから、西岡常一棟梁が法隆寺の技術が朝鮮半島を伝って渡来したのに対して薬師寺の技術は大陸から直接技術工法が伝わったのではないかと推測していました。半島を伝わらなかった分直接早く最新の大陸技術が伝わったのだというのです。為政者たちの動きを知る上でも貴重な推論でした。
天武天皇が皇后の病気平癒のために建てたその願い通り皇后は回復し天武亡き後持統天皇として代を繋げたほどに霊験ある薬師如来を安置しています。創建以来1300年にわたって生き抜いてきて、今回垂木や柱に多くの埋め木が施され補強なった東塔は新しい西塔と共に伽藍整いつつある薬師寺の顔として今後も奈良・大和路の歴史を紡いでいってくれると思います。
最後に吉野で南朝を開いた後醍醐帝が皇居として住んだといわれる吉水神社に足を延ばしました。南北朝に分かれて吉野に南朝を開いた後醍醐天皇がその住まい・皇居とした場所です。先の廃仏毀釈前までは吉水院という寺院で、天武帝の頃役行者が開いたとされる修験の僧房で1,300年の歴史があるとされます。その後57年ほど南朝は続くことになりますが、ここの玉座で後醍醐帝が政務を執り行ったのはたった2年ほどの間で、いつかは北の京都に戻る日を夢見ながら果てたことに思いを馳せます。そもそも後醍醐帝がこの吉野の地に南朝を張ったのも、壬申の乱で天智帝の大津京を倒した大海人皇子こと天武天皇が吉野にこもった古事に倣ったのだとされています。朝廷は二朝対立という不幸な南北朝時代が足利義満の時代まで続くことになります。
さらにもう一人、鎌倉幕府開府前夜頼朝に追われた義経一行が密かに身を寄せたのもここ吉水院でした。5日間潜伏したのち女人禁制の山に入るため静御前と永遠の別れをして、弁慶と共に山伏のいで立ちでここから平泉を目指したのでした。
この吉水神社からの眺めは格別です。北側には「一目千本」の立て看板通り山の奥まで桜の木々が続いて見える場所が用意されています。後年、晩年の太閤秀吉が吉野の大花見会を催しその本陣としたのも吉水院です。家康、利家、政宗らを従えた総勢5千人という規模で歌会・茶会・能の会を5日間に渡り盛大に催したといいます。
吉野に入った一行は当初3日間雨に見舞われ、明日も雨なら全山に火をつけて下山だと秀吉が怒ったことから吉野の全僧房がこぞって祈祷を行い翌日見事に晴れに転じたと伝わります。「年月を心にかけし吉野山花の盛りを今日見つるかな」の歌を詠んだ秀吉はこの吉野の花見をさぞや楽しみにしていたのでしょう。往時使った調度品がここに寄贈・展示され今に伝わります。
本来は花の見ごろの4月にでも来れば見応えがあるのでしょうが、投宿した宿坊の人の話しでは温暖化の影響なのか従前であれば下から中、上へと順次咲いていくはずの山桜が今は一斉に咲いてしまうとのことで、期間が短い分観光客が集中しその混みようは尋常でないとのことでした。その代わりに5月くらいの新緑の頃か9月の中秋の名月の頃が感動的でおすすめだとのことでした。
吉水神社からは一目千本の山側と反対の南側には街道を挟んで国宝・金峯山寺(きんぷせんじ)蔵王堂の重層入母屋檜皮葺屋根の威容が望めます。以前この稿でも紹介しましたが修験道の聖地として古くから崇敬を集めた蔵王堂は天正年間に再建されたものです。68本の柱が1本として同じ径がなく、樹種もつつじやカエデなど多種にわたる樹種が皮を落とした原木のまま使用されて圧倒されます。二手先組で持出された軒の深さ共々荒々しい中に大工の腕の確かさも感じずにはいられません。解体修理中の二王門共々国宝の名にふさわしい名建築物といえます。
忙しい大和路歩きでしたが、よく「大和は日本のふるさとである」といわれます。輝かしい古代文化の数々がこの地で生まれ古代の朝廷がここで栄え大和一国の名が日本全体を意味する言葉となったのですからもっともなことだといわねばなりません。
でもそんなことは知ってか知らずか、今の大和路は歴史を地面の下に埋没させて鄙でひっそりと佇んでいるように見えます。